さまざまな会議体
の議事録
業務ニーズにあった内容や体裁で自動作成
提供:株式会社ブーツ
事例紹介
JR西日本が生成AIで取り組む事業変革
業務課題の徹底分析と粘り強い伴走で
事業と人財の着実な変化へ
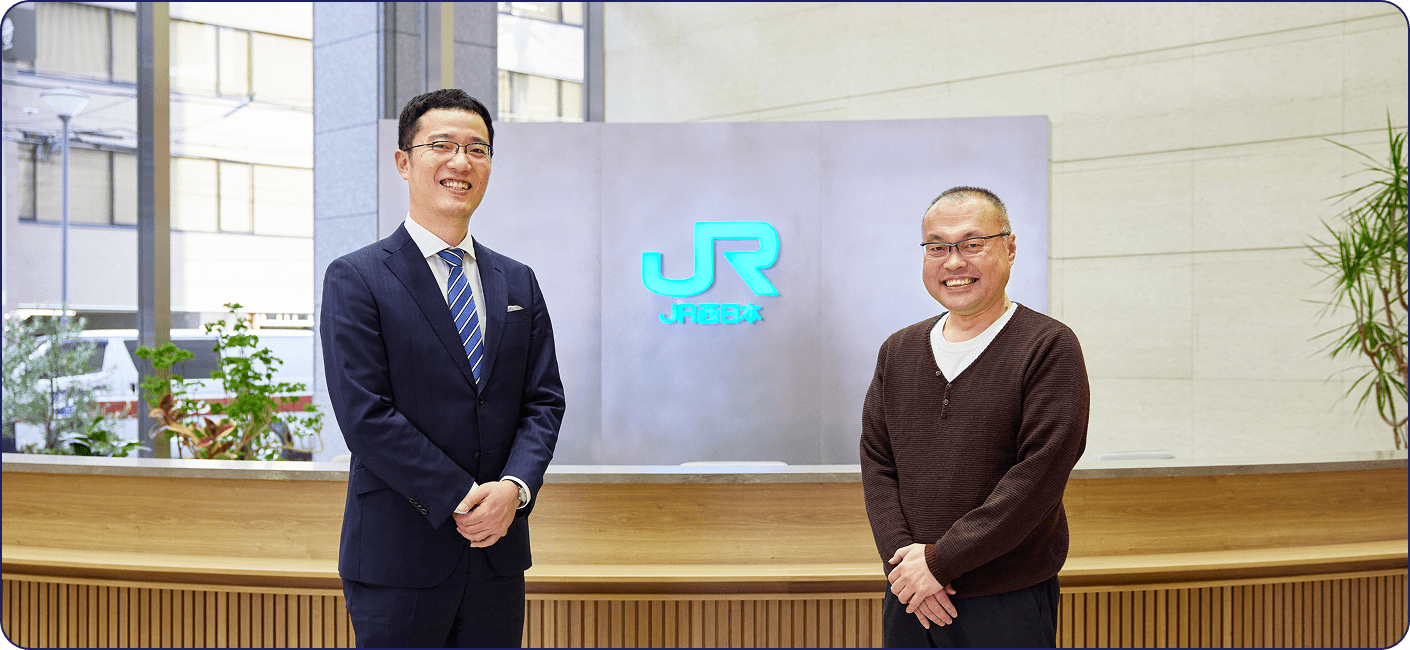
ブーツ / Boots,Inc.
代表取締役
有賀 啓介氏
JR西日本
デジタルソリューション本部
DX人財開発室長
高本 浩明氏
2024年11月から約4カ月にわたりJR西日本の本社部門約20部署を巻き込み、生成AIによる業務変革ユースケースの創出を軸としたDX推進プロジェクトを実施したブーツ。200を超えるアイデアから約60のプロトタイプ検証を実施し、生成AIが事業や業務、社員、組織に与える変化を手触り感をもって描き出した。プロジェクトを振り返り、ブーツ代表取締役 有賀啓介氏と、JR西日本 デジタルソリューション本部 DX人財開発室長 高本浩明氏が対談。DX推進の意義や本質、プロジェクトの成果などを語り合った。


ブーツ / Boots,Inc.
代表取締役 有賀 啓介氏
東京大学工学部卒業。三井物産(AI・DX領域の事業開発や経営企画業務)、アクセンチュア(戦略コンサルティング部門)、医療系DXスタートアップ企業の執行役員を経て株式会社ブーツを設立。事業や業務の課題に立脚して着実に変化を起こすためのDX経営コンサルティングサービスを展開。

JR西日本
デジタルソリューション本部
DX人財開発室長 高本 浩明氏
1993年JR西日本入社。本社 総合企画本部でICOCA電子マネー・山陽新幹線EX-ICなどの立ち上げ、営業本部、駅業務部にて関西公民鉄とのICOCA連携など主要プロジェクトに従事。2023年4月より現職。
有賀(ブーツ)御社でのDX推進は新型コロナウイルス禍が一つのきっかけだったと伺いました。
高本(JR西日本)コロナ禍で主軸の鉄道事業だけでなく関連事業も大きく影響を受けました。経営レベルで当社事業の強みを再考する機運が高まり、当社グループが持つ膨大なデータの潜在力を認識しました。
当社の事業とデジタル技術は親和性が高いと考え、2020年に「JR西日本グループデジタル戦略」を策定。3つの再構築(顧客体験・鉄道システム・従業員体験)を柱としてDXを推進しています。
有賀そのデジタル戦略の文脈でも、生成AIへの期待と注目が高まっているとおっしゃっていましたね。

高本はい、デジタル戦略ではまずMicrosoft365でコミュニケーションや意思決定の変革に取り組んだ後、Microsoft Power Platformによる内製開発などで現場のデジタル活用を促進してきました。生成AIはその次の3つ目のツールとして位置づけ、適切に活用すれば社内のデータと連携してグループ全体の事業や業務の効率化・高度化に大きく貢献すると期待しています。
ブーツ社には以前からDX人財育成のコンサルティングでお世話になっていましたが、今回は注目が高まる生成AIで弊社の業務をどう変革していけるか、ユースケースを具体化すべくご支援いただくことにしました。

有賀弊社ではDX推進支援を数多く手掛けてきましたが、今回のご支援で示唆深いのは、DX推進を”DX人財育成”の枠組みで推進してきたことです。
生成AIの技術的な特徴は、『高性能』であることに加え、『汎用性』が高く、技術として『パッケージ化』されていてエンジニアでなくとも様々な手法で業務プロセスに適用できることです。時代の潮流として、DXの成否のポイントが利用者や部署・組織、業務プロセスなどのいわゆる”人間系”が「どううまく取り込んで使いこなせるか」に移行してきており、DXを人財・組織の変化と両輪で進めることは非常に本質的だと感じています。
高本実はプロジェクト前は具体的なユースケースがどれだけ出るか不安もありました。しかし、業務を徹底的に分解・整理して業務課題の抽出から議論を進めるブーツさんのアプローチは、目からうろこでした。実は前年度にも生成AIの活用アイデアを出すイベントを行い、複数の実証実験にも取り組んできたのですが、今回は業務起点で議論することで有効なアイデアが多く生まれました。また、生成AIだけでなくPower Platformなどの様々なツールも組み合わせて一つでも多くの業務課題の解決を目指すことで、ユースケースの広がりにつながったと思います。
ワークショップの設計や検討のフレームワーク、事例や情報のインプットなど、すべて弊社の意図をくんでカスタマイズされたプログラムだという印象が強かったですね。

ワークショップ(集合研修)
幅広い領域の本社部門約20部署でプロジェクトを立ち上げ
事業・部署ごとの業務の課題やありたい姿の言語化、業務プロセス整理
基礎理解のインプット。生成AIやDXのツールを手触り感もって理解
課題に対する業務施策や
DXアプローチの議論の考え方・進め方を理解


個別伴走・個別アドバイス
それぞれの業務課題の分析やそれに対するDXのアプローチ(デジタルツールの活用方法、開発イメージ、ツール選定など)を個別で議論
※幅広いオプション:社内汎用AIチャット、Copilot for
M365、Copilot Studio、 Power
Platform(ローコードアプリ、RPAとAIの連携)、独自のシステム開発…など
プロトタイプの作成と検証を通じて活用方法やプロンプトを改善
200以上のアイディアから約60のユースケースを実際に検証

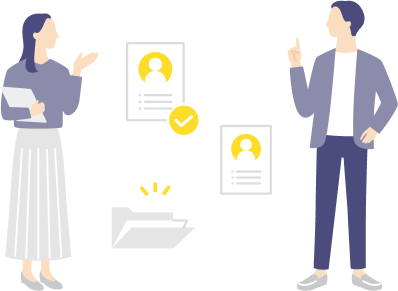
成果のとりまとめ
事業・業務における定性・定量の期待効果を整理
業務への導入から成果を出すまでのロードマップを具体化
社長や各部門の役員も参加した全社公開の成果発表会でAI活用方法や検証結果を共有
徹底した事業・業務プロセス目線の議論により、
参加全部署で業務に根付いた生成AI・DXのユースケースを創出

ワークショップの様子:プロジェクトの序盤で1dayのワークショップを実施し、生成AIの使い方から業務目線の検討プロセス・考え方まで、基本的な知識・理解を共有した。
有賀重視したのは「業務を起点に考える」「テクノロジーの手触り感をもって考える」という2点です。世間では生成AIへの様々な期待やイメージがありますが、実態としては生成AIが全てを完璧にできるわけではありません。「このタスクならこれくらいの精度でやってくれる」という手触り感が大事。それと業務目線を持つことができれば、実際の業務での活用方法を考えて工夫する思考のサイクルが生まれます。
高本以前は「生成AIで置き換えられる仕事はないか?」という発想でしたが、実際の業務の多くはそんなに単純ではありません。だからこそ、業務を分解して考える作業の重要性を実感しましたね。適用可能な範囲が明確になったほか、「そもそもこの業務は本当に必要か?」といった業務自体と改めて向き合う視点も得られました。
有賀業務目線で議論すると、解決したい課題や実現したいことが複数でてきます。課題が多数あれば、その解決のためのDXアプローチも多様になるので、様々なツールを使いこなすニーズがでてきます。
今回は社内の汎用生成AIチャットツールに加え、Copilot for Microsoft365やMicrosoft
Copilot Studio、ローコード業務アプリ、RPA、専用の生成AIアプリケーション開発なども選択肢として示しながら議論を進めました。

さまざまな会議体
の議事録
業務ニーズにあった内容や体裁で自動作成

社内外の
問い合わせの対応
社内情報に基づく
自動回答
複雑な申請書類の
チェックや対応を補助

社内情報の有効活用
大量の社内文書から必要なものを即座に参照し、
ナレッジ、ノウハウとして活用
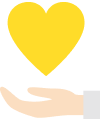
顧客サービスの
スタッフ支援
アナログな現場作業の軽減。
限られた人員で高品質に

企画系業務の支援
旅行商材やイベントの企画・提案の補助
複雑なスケジュール調整作業の補助

広告宣伝物の確認・
ブラッシュアップ
各種観点の内容・表現の事前チェック作業を補助
宣伝効果向上にむけた分析

お客様の声や
SNS投稿の分析
迅速・網羅的に対応
有効な改善策を導出して企画やサービスの向上へ

会議運営の品質向上
事前の論点整理、
資料ブラッシュアップ、会議後の要約・振り返り評価…など

監査・IRなど
大量の書類情報を効果的に分析。
有効な仮説の導出
書類作成、Q&A準備などの作業品質の向上
高本以前からある社内のチャットツールでできることがこんなにたくさんあると再認識できたことも、とても大きな収穫でした。業務分解の視点との組み合わせで、既存のツールを効果的に活用できると実感しました。

高本強力な伴走体制でのサポートも非常に心強かったですね。参加部署の誰も途中で脱落することなく2月の発表会までやりきることができました。グループ別の個別フォロー会や、宿題の添削など、毎週のように継続的なフォローアップをして丁寧に伴走いただけたことが大きかったです。随時チャットで相談できる仕組みも、参加者のモチベーション維持につながりました。
そうしたメソッドとは別に、泥臭さというか有賀さんの熱量も感じていました。参加者ごとにDXの理解度も異なる中、一人ひとりの目線感にあわせて丁寧に向き合う姿に、こちらの熱もおのずと高まりました。

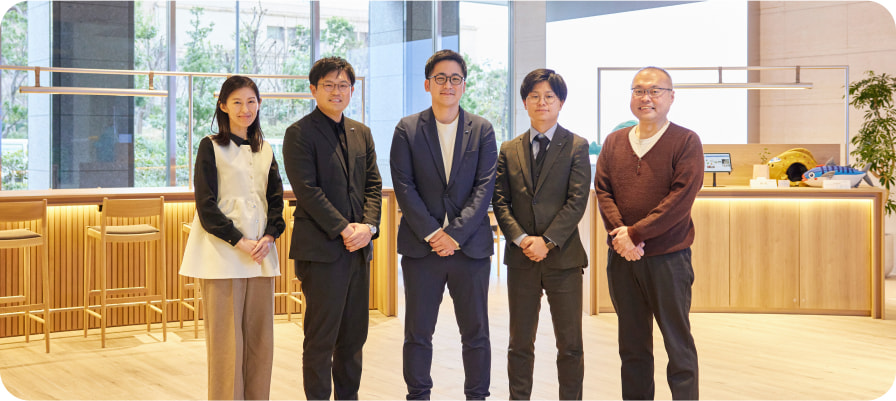
ブーツ社とともに生成AI・DXのユースケース創出をチーム一丸となり取り組んだDX人財開発室のメンバー
(左から、倉内課長、那須氏、松田氏、中司氏、高本室長)
有賀今回はこちらから一方的に教えるというより、参加者の思考や工夫を促す”コーチング”的な手法も交えて進めました。途中では「よく分からない」「難しい」と感じた参加者もいたかと思いますが、最終的に全ての部署でユースケースを創出できたことは私自身も嬉しかったです。
高本有賀さんがおっしゃる「手触り感」を、参加者自身が体感しているように感じました。

有賀今回は複数のDXツールを扱いましたが、業務の中でのそれぞれツールの有用性は型通りの機能説明などでは伝わりにくく、実際に業務で使ったり稼働したりしている様子を見て初めて実感できるんです。
各部署のユースケースのアイデアをもとに弊社で実際にアプリ作成などを行い、そのデモンストレーションやデモ動画の共有を行ったことで、実現のイメージを強く持つとともに、「この技術ならこの業務でも活用できるのでは」という発想の広がりも生まれたと思います。感覚的な理解や思考を促しながら、必要なツールを適切に選択できるようになっていただくことも意図して進めました。
高本プロジェクト後の参加者アンケートでも「伴走サポートに助けられた」という意見が多く全体として高評価でした。御社の強力な伴走があったからこそ、全部署で成果をまとめることができました。
有賀今回のプロジェクトでは、人財育成も大きなポイントでした。DXと人財育成の関係で私が本質だと考えるのは「DXが人財育成の機会になる」という観点です。
高本生成AIという汎用的なツールを扱う経験を通じて、関連する他のDXツールにも興味をもつ人が増え、社内全体のDX機運が高まったことは大きな変化でした。
有賀御社の皆様と関わらせていただく中で、業務文脈の中で正確に仕事を進める”オペレーショナル”な思考傾向が強いと感じていました。これは大切な企業文化である一方、多くの企業に共通するDXのハードルでもあります。
テクノロジーを補助線として使いながら、仕事の効率化や価値向上のためにどう工夫するか。この考え方を共有していくことが大切ですし、DXの面白さだと思っています。

高本おっしゃるとおり、弊社は真面目で手堅く仕事をする社員が多いですが、今回のプロジェクトでは隠れていた創造性をうまく表に引き出していただきました。
有賀一番大事な成果はユースケース自体よりもむしろ人の変化・成長だと思います。テクノロジーが日々急速に進化する中、現状のテクノロジーに詳しくなることがゴールではありません。
手触り感をもって新たなテクノロジーを理解してそれを業務目線で有効に取り入れていくスキルこそが”一生モノ”ですし、企業や組織にとって大きな財産となるはずです。
高本私も、「DXの主人公はDX推進部署ではなく全社各部署の社員全員である」と実感しています。JR西日本のグループ全社員約4万人がデジタル技術を活用できるようになれば、その効果は計り知れないですから。
実際、今回の中心となったマーケティングやカスタマーサクセス、コーポレートなどの本社部門では、記者会見のQ&A作成で作業時間を半減した事例や、市場分析で商品開発やプロモーションを改善する事例など、効果と説得力に富んだユースケースを各部署の社員が数多く生み出してくれました。

有賀鉄道関連部署の方々も、業務改善やお客様対応の品質向上につながるアイデアなど、具体的なユースケースを生み出しており、広がりがあると感じました。
高本広がりという点では、今回の発表会は社内にとどまらずグループ各社へも公開しました。社長をはじめ各部門の役員も参加して、当社のDX加速に向けて意義のある会になりました。
有賀並行してご支援している人財育成体系や生成AIガバナンス整備などについても、教科書的な議論ではなく、具体的なユースケースも念頭において他でもない御社の文脈の中で設計・運用していくことが大切だと思っています。
高本 今後の労働力減少時代に対応するためには、デジタル技術との共存が不可欠。業務の効率化にとどまらず、社員一人ひとりのパフォーマンスやワークエンゲージメントを上げていくこともDXの大きなミッションだと考えています。
今回の取り組みでそのミッションを果たせる確かな手応えを感じました。今後とも、ぜひよろしくお願いします。
※本プロジェクトは株式会社ブーツと株式会社セルム
での共同でのご支援です。


業務の現場と連携し、一歩一歩着実にDXを実現していく
コンサルティングサービスを提供
DXやAI活用に関する経営コンサルティング、AIアプリケーション/システム開発、人材育成・研修などを主軸としたDX支援事業を展開。ツールありきのデジタル化提案ではなく、事業や業務の課題に立脚し、業務プロセスの理解に基づいた実効性あるコンサル支援を実施。実際に業務を行う現場社員と丁寧に向き合う独自のアプローチで様々な企業や組織のDXを支援している。
お問い合わせはこちら:info@boots.co.jp
※2025年4月3日~2025年5月3日に日経電子版広告特集にて掲載したものを転載。
※著作・制作日本経済新聞社 (2025年日経電子版広告特集)。記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。